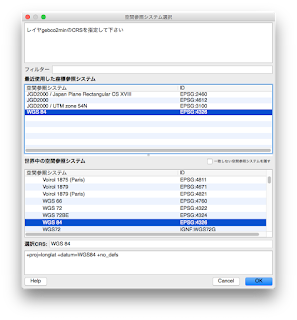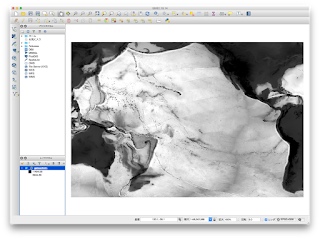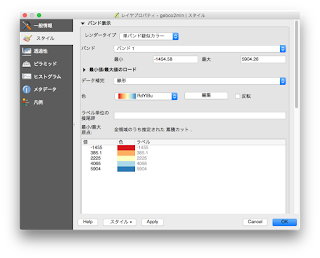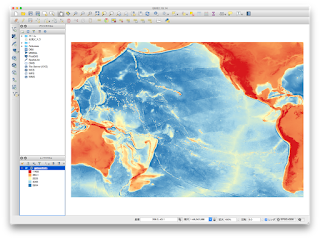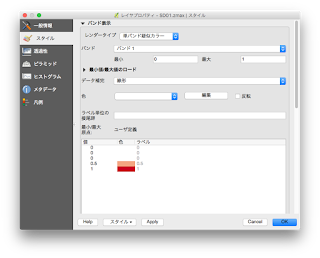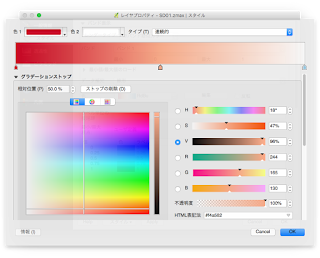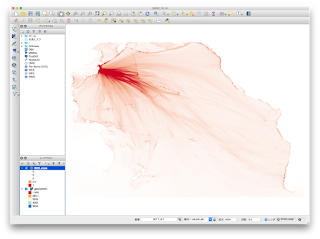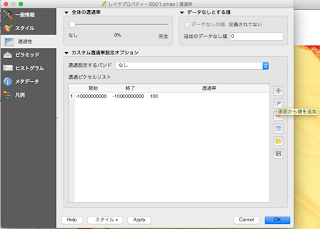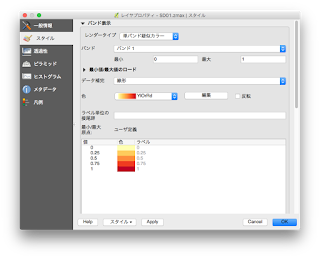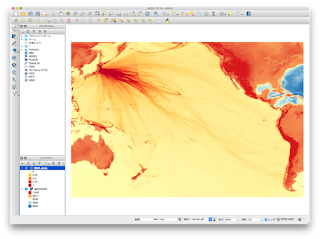More recent information on June 4, 2024, we need to prepare ourself proj because proj@7 has been disabled. It's still available if you are using MacPorts.
Error: proj@7 has been disabled because it is a versioned formula! It was disabled on 2024-02-12.
(2024.9.6追記)
LIBS=-L$(PROJ4_DIR)/lib -L$(NETCDF)/lib -lnetcdff -lnetcdf -lsz -lproj $(FFTW3_LIB) -lm
のように,homebrew で他のバージョンのprojが /usr/local 等に入っている場合,自分で入れたPROJ4のディレクトリを先にリンカに指定する必要がある.
2023年12月27日現在の macOS Ventura 13.6.3 + Homebrew でのJAGURSのコンパイルについて再整理しておく。
- gcc ... gfortran を使うので、gcc と gfortran をbrew で入れて、/usr/local/bin/gcc を使う。
- FC=/usr/local/bin/gfortran
- CC=/usr/local/bin/gcc
- /usr/local/bin/gcc は無さそうなので, /usr/local/bin/gcc-14
- proj ... メインのproj は、9.3.1 なので、おそらく動かない?ので、7.2.1 なproj@7 パッケージを使う。
- PROJ4_DIR=/usr/local/opt/proj@7
- netcdf ... netcdf-fortran パッケージを入れる
- fftw3 ... Homebrew のパッケージ名が fftw に変わってた
Makefile.gfortran をベースにして、以下の修正。
-FC=mpif90
+FC=/usr/local/bin/gfortran
-PROJ4_DIR=$(HOME)/local
-CC=gcc
+PROJ4_DIR=/usr/local/opt/proj@7
+CC=/usr/local/bin/gcc-13
-FFTW3_INCLUDE_DIR=$(HOME)/local/include
+FFTW3_INCLUDE_DIR=/usr/local/include
-NETCDF=$(HOME)/local
+NETCDF=/usr/local
-MPI=ON
+MPI=OFF
特殊な手続きは無しでコンパイル出来るようになったな。。。この記事の役割もほぼ終わったな。
input/ の中でそのままテスト計算(MPI部分はtsun.parから削除) on 1.4GHz dual cores Core i7
../src/jagurs par=tsun.par 4113.94s user 52.32s system 120% cpu 57:42.04 total